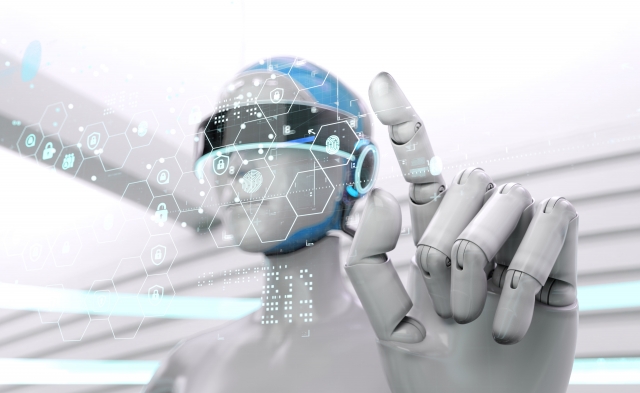骨の袋
テレビシリーズの前編後編で放映されたそうだが、それにしては手の込んだ作品だ。いろいろなレビューを見るとけっこう言われちまっているが、まあそういうのは教養にして、私なりに受けた感想でも書いていこうと思う。
まず私自身の悲劇だったのは、後編から見てしまったことだった。テレビシリーズだから後編であってもオープニングがしっかりあったので、何の気なしに見続けてしまったのだ。そしてラストまでみてしまうと、さあて、スティーブン・キングはここからさらにハプニングをどう用意してくるのかな、などと、前編を見始めたのだった…。最初は辻褄が妙に噛み合わなくて、回想シーンなのかと思ってみていたが、徐々にまさか前編ではないか、と思った時にはまったく気づきもせずに後編を見通していた自分自身に驚愕した。アホとか言われたりするような類いであることは間違いない。だが、私の特技というか、曲がった性分というか、あんまりそういうてんこちゃんこな映画の見方をしても、気にしないところがある。
幼少の頃、ビデオもなかった時代、テレビで映画をやっていても、オヤジが野球をみていて延長戦になったりすると、二十分くらいはロスしたりすることはよくあった。それでも想像力を働かせて、文脈を作り上げて、ロストされた冒頭を脳内で勝手に補完することは難しくはなかった。
「マチネー」という映画が昔あって、そのなかで昼の映画館がタイトル通り出てくるのだが、映画を見ているというよりも、映画なんかは中途半端で、ロビーでポップコーンを頬張ったり、その空間を楽しみ暇を潰すシーンが盛り込まれていた記憶がある。それを見たときに、ああ俺の映画の見方ってこういう感じだなあ、というような印象を受けたのを思い出した。そもそもマチネーで上映されていたのは三文スリラーで、真剣に見る必要なんかはないのだろうけれども。
骨の袋にはそんないい加減にみていいようには作られてはいないのだけれども、結果的には重要なシーンは要所にしかない。飛ばしてみてもストーリーはつかめるようになっているといえるだろうか。アメリカのドラマが優れているのは、どこからみても楽しめるようになっているところだ。ドラマサスペンス「24」なんかは本当によくできている。セリフの中に、途中から見た人間にもわかるように解説が含まれている。それらを重複として嫌がる人も中にはいるだろうが、筋立てを見失わせないようにするには最良の方法であり、ストーリーの柱がぶれないようにする製作サイドの自己暗示でもあるだろう。この手法がなければただのマニア向けのドラマになってしまって、大成を勝ち取ることはなかったと思っている。
骨の袋にはそういう技巧はしっかりと組み込まれていて、私のようなトンマが後編からみてもすんなりと見れてしまうような配慮がなされているのだ…。(しかしまさか後編からみてしまう人のためにも配慮するか、と思う人がいるかもしれないが、テレビでやる以上は、視聴率のためにも必須のことだろう)
閑話休題、本編の話にしよう。ストーリーの構成から話せば、呪いが人々を悩ませ、巻き込まれた主人公が悪霊を沈めさせる、というだけのストーリーだ。ただここに込められたのは、悲しみ、という大きなテーマである。骨の袋をみてチープだなと思った人は多いかもしれない。実際に目新しいトリックもなく、どれもよく知れたスリラーの手法ばかりだ。ラップ現象なんてもう最近はいう人も少なくなったんじゃないだろうか。そんな古典的な現象が並べられている。しかしそんなことを批判する必要はない。もっと大事な主題があり、どちらかというと小説としてのテーマを残していて、それを軸として、スリラー好きの不特定多数にもメッセージが伝わればよいな、という意図が私には見受けられる。悲しみ、という厚みのあるテーマを、どうやって多くの人にみてもらうか、そのためのスリラーとこの骨の袋ではいえる。
ではどこが悲しみであり、小説的なのかということを軸に話してみたい。
悲しみというのはずばり消失のことだ。単に妻を亡くした夫の悲しみだ。もうひとつは無念に殺された母と子のもつ悲しみだ。そんなことがなんだというかもしれないが、こんな悲惨なことを挙げ連ねたドラマもあまり無い。あったとしても、妊娠中の妻が死ぬ、のと、レイプを子供に目撃されながら、その子供が窒息死させられ、自分も撲殺される、というようなことを組み合わせるようなことは、そうそうない。もしこの骨の袋をみても、そのあたりの悲惨さを、ただの作り物の中でのことだとして冷静に見ていられるようならば、どこかが麻痺していると思っていいだろう。感情を素直に注げば、なんていう悲劇だと思わざるを得ないはずだ。そんな悲劇をうまく噛み合わせているところがスティーブン・キングの妙技だろう。
子を待望した妻と胎児の死と、壮絶な強姦死と娘の溺死を味わった母親の並列。この悲しみと、愛を歪曲させてしまう男たちとの対比。それにスリラーを付け足したもの、と言えば分解しやすい。
これをただのスリラーにできる限りの悲惨さを付け足したもの、と読み違えてしまうと捉え方は大きく異なってしまう。はっきり言っておく。この物語は小説を読むときの構えで挑まなければ、理解できない。スティーブン・キングの作品にはエンターテイメントな要素が多いがあくまでもライターであることを意識していることが見受けられる。まず劇中のマイク(ピアース・ブロスナン)がライターであること。これがなんの意味を持つかといえば、優しさ、だと私は思う。おそらく主人公をたてるときに、スティーブン・キングは考えるんじゃないだろうか、結局、ひどい目に合わせる主人公は僕でいい、と。飛躍しすぎかもしれないが、それぐらいの愛がなければ小説なんてものは書けまい。また、劇中で自分を励ましながらなんとか筆を進めるシーンがある。あれはスティーブン・キング自身であり、スティーブン・キングが「自分のこと以外を書くことはできない」とでも悩んでいるかのような姿である。ここは分かりづらいので、もう少し噛み砕いてみよう。
劇中の主人公がライターであることは、スティーブン・キングが、自分を中心とした物語しか書けない、という現れだと思っていいだろう。ここで言う「書けない」というのは本当に書くことができないわけではくて、どんな物語でもフィクションでも、必ず作者が投影されてしまうことに気がついている、ということをまとめた私の表現としてとらえてほしい。「キャリー」は女の子だったし、「デッドゾーン」では学校の教師である。なんでも書けるが、やっぱり詰まるところ、作家であることを越えることは、できない、という小説家のジレンマ的な本質を相当に自覚してるはずだ。ピカソが絵のなかで「画家とモデル」をテーマにしたことと同義だとして差し支えないだろう。
小説というのは、小人の説、という意味だ。ある、ただの人の小言、と言ってもいいだろう。スティーブン・キングもあるただの小人のひとりであり、その個人的な小言をいっているにすぎない、としっかり自覚しているのである。と、私は勝手にとらえている。
ベストセラー作家で4位の主人公であるが、スティーブン・キングもベストセラー作家であることから、これを嫌みに捉えたりすることは必要ない。どんなベストセラー作家であっても悲しみや障害に出くわしてスランプに陥ることだってあるのだ、ということを表していて、自身はただの人である、ということが言いたいのだと思えばいい。そうすることによって、感情の移入がスムーズになり、悲しみというテーマがより捉えやすくなる。
つまり、小説家でありただの一人の人間というスティーブン・キングの自覚が物語全般の大きな柱になっている。
そして悲しみというテーマは、小説とスリラーをつなぐ大きな役割になっている。役割というと変だが、スリラーを物語として成立させるためには、テーマが必要で、スリラーがテーマになるわけではない。ここが大事なところで、スリラーをテーマにしただけの物語もあるかもしれないが、それは小説にはならないだろう代物であって、およそスティーブン・キングが求めるようなものではない。よってこのドラマをスリラーのうんぬんで評価してしまうとそりゃあチープなものになってしまうのは必至だ。「デッドゾーン」の何話目かはわからないが、主人公が、あるSFライター志望の少年がなかなかコンクールで選ばれなくて悩んでいるのを透視したときに、「続けていればいつかきっと成功する」と助言した。これはスティーブン・キングの優しさと、自分自身へのエールでもある。小説にはこの優しさという愛が必要である。また、この優しさは、他人の悲しみや怒りを受け止め考え続けなければならない力のことだ。その作業は考えているよりも大変な作業であって、おそらく一番スティーブン・キングを悩ませ疲労させていることなのだろう。スティーブン・キングはスリラーの大御所となってしまっているが、真に描いているのは「人の心」である。そしてその対象というのは常に弱いものであって、彼らの立場に身を置いて、物語を書いているのだ。
ピアース・ブロスナン
主人公を演じているピアース・ブロスナンは、渋い二枚目の五代目ジェームズ・ボンドであるが、この骨の袋の役にもしっくりきている。女たらしで知性的なモテ男が設定されているこの主人公に、他の誰があてはまるのか候補をお持ちであれば教えてもらいたい。
個人的にジェームズ・ボンドも、彼が一番しっくりきていると思う。ショーン・コネリーとかロジャー・ムーアはコミカルすぎたりやせぎす過ぎたりなんかピンクパンサーのアニメに出てくるような風体でなんかカッコ悪い。ダニエル・クレイグなんかは敵役の方が活きると思う。ところがピアース・ブロスナンは、この年寄りの私からイメージするジェームズ・ボンドにピッタリの配役だったと思っている。スーツの着こなし、ドライビングスタイル、胸板の厚み、どれをとっても歴代のボンド役の中で一番光っている。
ボンドはさておき、ピアース・ブロスナンだからこそ、あの狂った富豪デヴォアに立ち向かう演技をこなしたし、囲う美人たちとも釣り合いがとれたのだ。まあ役者のことはどうでもいいか。しかし女たらしの作家である。美人な妻を亡くしたばかりで、若くまた美しい未亡人ともデキていて、さらに亡霊からも誘惑されるというんだから、嫌気がさす人もいるんじゃないだろうか。しかしいずれも主人公マイクからは手を出してはいないし、どちらかというと妻の亡霊があのダークスコアレークへとマイクを呼び寄せて仕組んだようなところがあることは忘れてはならない。そうしないとただのスケベが悪霊に罰を受けて、困ったところで悪霊を退治したと捉えかねないからだ。この物語で描写されていない霊界が実はバックヤードで忙しく想像を働かせてくれている仕掛けがある。妻からの応答があり、その直後にラップ現象がある。これはなんとなく妻と呪いをかけた亡霊との闘いか、話し合いの行き違いのようなものを表している。妻がベッドのしたで引きずり込まれていくのもそれに近い。まさかこれらを貞子とかのような意味なしホラーと見比べてしまったりしないように。一見チープなスリラーだが、意味がちゃんとある。若い未亡人が脳を吹き飛ばされて現れるのも、過去の祭りに入り込んでしまうのも、霊界では時空をこえて未来過去へ複雑にアクセスできる設定を作り上げている。これはフィクションを信じている作家にしか体験できないものであったりしたのかもしれない。
そうして考えてみると、他の呪いをかけられた男たちはどうやって娘の殺害にまで運ばれたのだろうか。想像でしかないが、悪霊の言うままに殺害へと誘われたんじゃないだろうか。マイクの場合、妻の助けと作家である想像力で解決まで辿り着けたのだろう。妻からのメッセージを解読するには、相当な読解力と好奇心が必要だ。読解力も好奇心も誰の助けもない人間は悪霊に簡単に取り込まれてしまったのだろう。
確証はないが、妻は未来を半分知っていたのだということも挙げておく。霊界ではたぶん未亡人が死んでしまう運命であることもわかっていたし、悪霊を成仏させなければ、子供を助けることもできないこともわかっていたのじゃないだろうか。それを知っていての妻のアクションであらなければ、辻褄が合わないところがある。未亡人はたぶん、妻がとりついていたかもしれない、というのは飛躍しすぎだが、妻には親を失う子供を助けるように夫を促し、生まれなかった子供の代わりに、救った子供を夫に与えるという意図があったかもしれない。あくまでも推測だが、これくらい妄想しなければスティーブン・キングは楽しめない。
他にぶっとんだ妄想があればどんどん教えてほしい。
強姦され撲殺される歌手
歌手テッドウェルは悲惨な死を遂げたが、果たして被害者なのだろうか。殺された時点では完全な被害者だが、亡霊となってから呪いを施行してからは加害者である。たとえどんな仕打ちを受けたにせよ、幼い子供を溺死させるような考えは持ってはいけない。中にはこの歌手の立場を被害者として受け止め、悪霊に仕立て挙げられていると考える人もいるかもしれない。しかし呪いなら強姦に関わった男たち本人にかければよかった。子供を殺させちゃ、あなたも同じでしょ。あるいはもっと重罪でしょ。と私は考えるがどうだろうか。
しかし呪いというものはそんな風に理不尽であってかまわない。呪いはただの個人的な恨みであり、その定義などはない。自由に怨んで呪っていいのだ。人の心とは時に理不尽で不条理で狂気にまみれている。それらが暴れだしたときに良心が働いて沈めてくれる。良心がうまく働いてくれればだが、怒りと悲しみに満ちてしまった歌手にはもはや良心などは持ち得なかったのかもしれない。
悪霊と化した歌手とその子供の遺体を掘り起こし、薬品で溶かすシーンがある。土葬の習慣があるからか、焼こうとは考えないのだろうか。「スーパーナチュラル」ではよく遺体を焼いて成仏させていた。ちょっと込み入った怪奇ものでないと、火葬が取り扱われないのかもしれない。記憶のなかではけっこう焼いたりしてるようなきがするのだが、「フライトナイト」のヴァンパイアも焼かれてた記憶があるが、たしか日光で浄化されてたよな、と火葬のある映画を思い出そうとしてもあるようでなかなか出てこなかった。この土葬文化が産み出したのがゾンビであって、日本の場合、骨壺に骨として埋葬される文化からでは到達しづらい発想だったように思える。火葬が当たり前の日本では、もしかすると死後の呪いが横行していて、慣例として焼くようになったりしたんだろうか、などと想像を馳せてみた。そうだとすると、西洋では呪いが未だ浄化されずにフラフラとしているのかもなあ、とさらに妄想を独り歩きさせてしまった。
気になるのは、ダークスコアレークが舞台であるのに、湖の登場が異様に少ない。もう少し湖にミステリアスな部分があってもよかった気がする。
骨の袋というタイトルは、マイクが言っているようにトマス・ハーディの引用からきている。
Compared to the dullest human being actually walking about on the face of the earth and casting his shadow there, the most brilliantly drawn character in a novel is but a bag of bones.
地の表面を歩くだけのダレている人間たちやそこに落とす彼らの影なんかと比べても、小説中でうまく描かれた登場人物なんかはただの骨の袋だ。(個人的な訳)
とでも訳せばいいだろうか。作られた架空の人物よりも生身の人間の方が魅力的だといっているわけだな。このストーリーの中ではさらに、意味を転じて、生きている以上は自分の方が、悪霊よりもましで、実体のない悪霊というものはただの骨の袋なんだ、ということにもなる。つまり実体のない架空の小説の登場人物と掛けているのだ。これはスティーブン・キングがスリラーの大衆作家と言われていても小説を意識していることを表していると言える。
もう一度トマス・ハーディの言葉に戻ってみよう。骨の袋とはなんだろう。想像は一度、文字通り、骨を入れる袋から考えてみる。かつて、ハーディがいた時代のイングランドでは骨を袋に入れる習慣があったりしたのだろうか。調べてみても簡単には出てこない。やはり比喩なんだろうか。ならばこうか。骨は死んだ人を指すこともできる。あるいは心ももたないただのカルシウムとも言える。袋とは言葉で脚色した登場人物の表面のことだろうか。肉付けされているようで、中身がないというかな。
ハーディの言葉を理解しようとするとある程度想像が働くはずである。骨の袋ってなんだ?とスティーブン・キングは彼なりの新鮮な読解力をもって考えていったんじゃないだろうか。そうすると彼の専門であるスリラーに出てくる悪霊も、小説で扱う登場人物たちも、みな、骨の袋のようだ、と気がついたのではないだろうか。実際はわからない。だが私はこうして妄想を働かせていくのが好きだし、妄想にはなにも得るものがないというわけでもない。もし私の妄想を仮説として話を進めていくと、さらに複雑になっていく。
主人公マイケル・ヌーナン、彼もまた物語の主人公であって、物語の中で作家として小説を書いている。そしてハーディの引用をし、登場人物なんて骨の袋だという。観客にとって、いやもとい、生身の人間にとっては、骨の袋に出てくる人びとや悪霊も含めたすべてのキャラクターが「骨の袋」になるのだ。
骨の袋。それは脳も心もないただのカルシウムでできたガラクタなのかもしれない。それをどんな飾られた袋に入れたところで、魂が宿るわけではない。まだ私の方がましだというわけだ、たとえマスターベーションしか繰り返さないサルに近い人間だとしても。