ゼロ・グラビティ。
無重力という意味だ。これは邦題であって、グラビティというだけのシンプルなタイトルが原題である。
原題は「重力」というだけのタイトルに対して邦題の「無重力」としたのはなぜなんだろうか。ここには重大な違いがある。決して間違っているということで言っているのではなく、真になぜなんだろうか、と疑問が沸いてくる違いがある。その考察は最後に回して、先にこの味わい深いストーリーを分解して行ってみよう。
今回分解していくのは以下の3筋。それと最後にタイトルを考察してみたい。
・娘の話
・犬の話
・神の話
・タイトルの考察
娘の話
まず娘の話から。主人公の ライアン・ストーン博士は娘が四歳で死んでしまった、と緊急事態でも陽気に話続けるマット・コワルスキーへ告げる。どうしてこんな話がストーリーに必要だったのか、単刀直入に言えば、
・宇宙→天国
という大きな筋がこのストーリーにはあるからだ。
途中、ライアンが神に祈ろうとするシーンがあるが、彼女は祈り方を知らない。科学者で、信仰心がなく、四歳の子供を失っている、というこの設定は映画「 レッド・ライト 」でも考察したように、御約束のようなもので、キリスト教圏では命題である救いはあるのかないのか、を語るにはもってこいの設定のようだ。
天国、つまり神がいるのかいないのかという問いが込められていると思ってこの映画をもう一度見直せば、難解に思えたり一本調子で退屈だと感じたりCGばかりに目がいって焦点を失ってしまうということもなく観ることが出来るだろう。
毎度だが私はキリスト教信者でも勧誘者でもないと断っておきたい。どちらかというと宗教には懐疑的な立場だ。しかしよくも知らないのに簡単に批判をしたくないので目下勉強中である(一生理解することは出来ないだろうが)。
ライアンの娘は天国にいる、そう考えられるのならあなたは信仰を持っていると言えるだろう。実際には天国なんかはない。誰も見たことがない。単に証拠がないというだけでなく、天国は科学的根拠もない眉唾物だ。しかし天国があると思うだけで、どれだけ気が楽になれるものがあるのだろう。死別、苦境、悲しみ、孤独。みんな死んだらパッと消えてなくなるものだ。ただの気持ちであり死ねば無くなるだけの空気より軽く空気よりも透明なものだ。だが、それらが消えてしまう、と言われただけでも、とても味気なく感じるのもまた人間だろう。愛をくべた誰かが先に死んでいるならばよっぽど、死後に再会できたらなと願うのが人間という生き物がもつ思考のシステムだ。あらゆる信仰の始まりはこの人間の弱さにあって、またそれを救おうとするところから始まりもし広まっていったんだと思っている。
映画は、そういった因習的な宗教や存在のあやふやな救いを、助長するか裏切るのか、古今東西いろいろな迫り型があって楽しい。多くの作品は生きるということに深くメスを入れ、忘れ得ない傷を脳に作っていってくれる優しくて温かいものだ。
この「ゼロ・グラビティ」ではあらゆる死と死が目の前を通りすぎていく。仲間の死。自身の死の危険、生への諦め。便りにしていたマットの自決。娘の死。宇宙は地獄のような世界だ。なにもない。音も空気さえもない永遠の空間または闇。
「君はここに残りたいか? 何も君を襲うものはないし、美しい景色もあるし」と幻覚のなかでマットは言う。この言葉だけを聞いたならば、こうも聞こえてはこないだろうか。
空の上にあり、美しい世界、恐れもない、永遠の時間が邪魔されることのない世界、、、
つまり天国とかそういった世界を描写するときに使われる言葉だ。宇宙はまさに天の上にあって、宇宙を知らない古代の者たちもが思い描いた天国だ。お花畑こそないが、眼下に見える地球の美しさはきっとお花畑にも勝るだろう。
しかし天国という、聞こえのいい場所にいるはずなのに、宇宙ゴミは襲ってくるし、生きる糧の酸素は燃焼して家である宇宙ステーションを焼くし、空間というか闇そのものは人を飲み込んだら二度と吐き出してはくれない。想像していた天国とは全く違う。
そう、天国などはないし、宇宙とは生身の人間を受け入れてくれるような世界ではない。死の世界、あるいは神の世界とでも言えばいいのだろうか。
はて、死んでしまった娘がいるのはこのような世界なのか。
ライアンはマットの幻覚を見たかもしれないが、それは紛れもなくライアンの内側から発生したものである。超常現象でもなんでもない。マットが言ったことはすべてライアンが脳のどこかに備えていたものだ。
取り戻したライアンはマットにこう投げ掛けるところがある。
「娘に伝えてほしいことがある。靴はみつけたよ、そしてとてもとても誇りに思っていると」
ライアンが、死が何であり、天国が何であり、信仰が何であり、地球という現実世界が何であるかを知った瞬間だ。死は確かに生物としての生命が維持できなくなった状態だ。だが人間の死とは単なる生物の命の終わりではない。少なくとも人間が心を持っていることは確実だ。この心というものは法則を持ってもいれば型も破るし時には狂ったりもする。幸か不幸かともかくそれが人間という生き物の宿主である。ライアンは心によって娘の死を悼んだ。また、その悼んだ心によって死を受け入れなければならない。これは科学でもあれば科学でもない。心とは物質でもなければ現象とも言いがたい無形不可視のものだ。心を見たものはいない。心を目で見た者などいるのだろうか。そんな者はない。芸術や宗教やなにかを通して心を垣間見ることはあったとしても、心そのものを見ることなどはできないのだ。これはなにかと似ていないだろうか。
ライアンは信仰を持たないで今まで来た。しかしマットが彼自身の死と引き換えに差し出してくれた生きるというチャンス、そして目の前に迫る死。もし神がいるのだったら、どうしてこんなことをするのだろうか。どうして救おうとしないのだろうか。信仰を持たなかったからだろうか。そんなことはない。神の前では犯罪者であっても皆平等のはずだ。しかし、我々は神を見たことがない。神などは現れ出てこない限りはこの世にいやしないのだ。では見えないものすべては信じられることなどなにもないのか、というとそんなことはない。ちゃんとある。それは力だ。この無重力である自由空間の天国(宇宙)、そこにはない力。引き寄せる力、地球からの引力がライアンを引き戻そうとしている。つまり重力だ。この世には四つの力があるという。磁力、原子と分子を構成している強い力と弱い力、そして重力。とくに重力だけは次元を越えて存在できるという。この映画に限っては、神(=天国がある)の存在を問うというテーゼに対する答えに、神、というか、有り難み、というか、真に信じていいもの、それが重力である、と言っているような気がしてくる。天や外にではなく、地球の内側にそれはあるのだと。
私はこの映画から心にも重力がかかるのだということを気づかされた気がしている。地球という重力が心を引き付け、感動させているのだと。娘の話が引き合いに出されているのはこのことを語るためだろう。天国はあるのかないのか、神はいるのかいないのか、救いはあるのかないのか。日本ではあまり重要ではないかもしれないが、キリスト教文化圏では重要なトピックスだ。この映画はキリスト教が抱えている問題に問題提起をし、この映画なりの答えを打ち出してくれている。映画「レッド・ライト」を考察したときにもこの辺りは語ったので、省略して記すが、この映画を観たあとでもう一度重力を感じてみてほしい。今度は娘を失ったライアンの気持ちになってみてだ。そのとき足元を見て重力を考えるのではなく、あなたの心にGがかかっているかどうかを確認してみるといい。その重さこそがあなたの良心であり、優しさだ。そこには必ず神が宿っているはずなのだ。






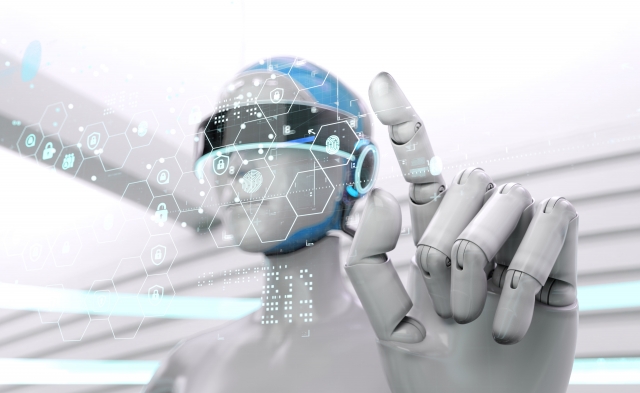
初めまして。映画ランナーというブログで好き勝手に映画レビューを書いている者です。
『』ゼロ・グラビティ』のレビューをお褒め頂き、誠にありがとうございます。本人の知らないところでこのように言って頂けたことに正直ビックリしております。
大変嬉しかったです。
コメントありがとうございます。
胎児説に説得力がありました。技巧への解説が散見できる中、読み応えがありました。他の記事も読まさせて頂いております。